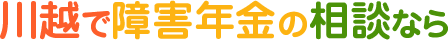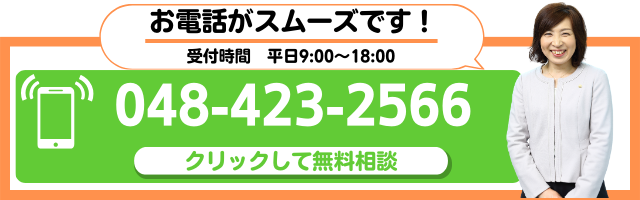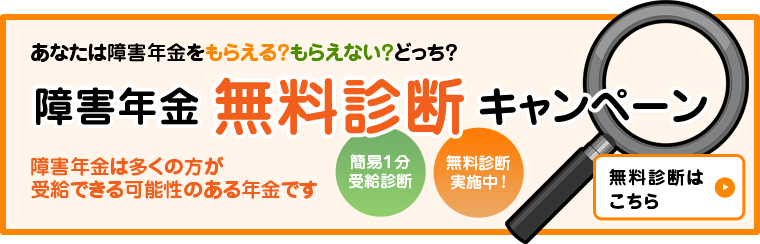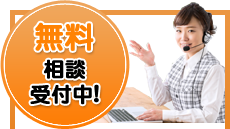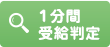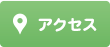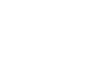人工肛門(ストーマ)で障害年金はもらえる?受給要件や金額、申請方法を専門家が徹底解説
目次
「人工肛門(ストーマ)を造設したけれど、今後の生活や仕事はどうなるのだろう…」
「障害年金がもらえると聞いたけど、自分も対象になるのか?手続きも難しそうで不安だ…」
このようなお悩みや疑問を抱えていらっしゃいませんか?
人工肛門を造設された方の多くは、日常生活に大きな変化が生じ、身体的にも精神的にも大きなご負担を感じていらっしゃることと思います。障害年金は、そのような方々の生活を支えるための大切な公的制度です。
障害年金の専門家である社会保険労務士が、人工肛門(ストーマ)で障害年金を受給するための条件や金額、申請の具体的な流れについて、どこよりも分かりやすく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
人工肛門(ストーマ)でも障害年金は受給できます!
結論からお伝えすると、人工肛門(ストーマ)を造設した方は、障害年金の支給対象となります。
障害年金は、病気やケガによって、日常生活や仕事に支障が出ている方のための所得保障制度です。人工肛門の造設は、日本年金機構が定める障害の状態に該当するため、要件を満たせば障害年金を受給することが可能です。
【重要】障害年金の認定基準と等級
「人工肛門になったら、必ず障害年金がもらえるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。障害年金を受給するためには、国が定める「障害認定基準」を満たす必要があります。
人工肛門は原則「障害等級3級」
人工肛門を造設した場合、原則として障害等級3級に認定されます。初診日に 障害厚生年金に加入していた方が対象となります。
「国民年金にしか入っていなかった自分はもらえないのか…」と諦めるのはまだ早いです。人工肛門の状態によっては、さらに上位の等級に認定される可能性があります。
2級以上に認定されるケースとは?
初診日に国民年金に加入していた方は、障害基礎年金を請求することになりますが、障害基礎年金は、原則として2級以上でなければ支給されません。つまり、障害等級3級とはならないのです。しかし、人工肛門を造設された方でも、以下のような場合は総合的に判断され、障害等級2級以上に認定される可能性があります。
- 人工肛門とあわせて新膀胱を造設した場合
- 尿路変更術を施した場合で、かつ日常生活に著しい支障がある場合
- 完全排尿障害(常にカテーテル留置や自己導尿が必要)の状態にある場合
- 人工肛門の他に、別の部位にも障害がある場合(例:手足の障害、精神疾患など)
このように、他の障害や症状とあわせて総合的に判断されることで、2級以上に認定されるケースは少なくありません。
【注意】身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は別物です!
よく混同されがちですが、身体障害者手帳の等級と、障害年金の等級は審査基準が全く異なります。「身体障害者手帳が4級だから、障害年金はもらえない」とご自身で判断せず、一度専門家にご相談ください。
受給できる障害年金の金額はいくら?
受給できる年金額は、障害の等級や年金の加入状況、ご家族の状況によって異なります。ここでは、2025年度(令和7年度)の年金額の目安をご紹介します。
障害基礎年金の年金額(目安)
- 1級:1039,625円+子の加算
- 2級:831,700円+子の加算
※子の加算:18歳年度末までの子(障害のある子の場合は20歳未満)がいる場合に加算されます。 (第1子・第2子:各239,300円、第3子以降:各79,800円)
障害厚生年金の年金額(目安)
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして支給されます。金額は、これまでの厚生年金の加入期間や給与(標準報酬月額)によって一人ひとり異なります。
- 1級: (報酬比例の年金額) × 1.25 + 障害基礎年金1級
- 2級: (報酬比例の年金額) + 障害基礎年金2級
- 3級: (報酬比例の年金額) ※最低保障額 623,800円
※配偶者加給年金:1級・2級に該当し、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に約234,800円が加算されます。
障害年金申請の6つのステップ
障害年金の申請は、ご自身で進めることも可能ですが、書類の準備が複雑で時間がかかることも事実です。ここでは、申請から受給までの大まかな流れを6つのステップで解説します。
【特例あり】申請のタイミングについて
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から申請できます。しかし、人工肛門を造設した場合は特例があり、造設日から6ヶ月が経過した日以降であれば、1年6ヶ月を待たずに申請することが可能です。
申請の6ステップ
- 年金事務所で初回相談・受給資格の確認 お近くの年金事務所や市区町村の年金窓口で、保険料の納付状況などの受給資格を確認します。
- 初診日を証明する書類の取得 初診の医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼し、初診日を証明します。
- 診断書の作成を医師に依頼 現在の主治医に、人工肛門用の障害年金診断書の作成を依頼します。
- 病歴・就労状況等申立書の作成 発症から現在までの経緯や、日常生活で困っていることをご自身の言葉で記述します。これは非常に重要な書類です(後述します)。
- 必要書類の提出 準備した全ての書類を、年金事務所または市区町村の窓口に提出します。
- 審査・受給決定 提出後、日本年金機構で審査が行われます。審査期間は数ヶ月かかり、決定すると「年金証書」が郵送で届きます。
申請でつまずかないための3つの重要ポイント
障害年金申請をスムーズに進め、ご自身の状態に見合った正当な等級認定を受けるためには、押さえておくべき重要なポイントが3つあります。
ポイント1:初診日の証明が最も重要!
障害年金申請において、初診日の証明は非常に重要です。初診日が確定しないと、保険料の納付要件を満たしているか、どの年金制度の対象になるかが決まらず、申請手続きを進めることができません。カルテが破棄されているなど、証明が難しい場合でも諦めずに専門家へご相談ください。
ポイント2:診断書の内容を必ず確認する
診断書は、障害等級を決定する上で最も影響力のある書類です。しかし、多忙な医師は、患者さんの日常生活の困難さまでを詳細に把握しているわけではありません。日常生活でどのようなことに、どの程度困っているかをまとめたメモを事前に作成し、医師にお渡しすることをお勧めします。
ポイント3:病歴・就労状況等申立書で「困難さ」を具体的に伝える
診断書だけでは伝えきれない、日常生活や仕事上の支障を具体的にアピールできるのが「病歴・就労状況等申立書」です。人工肛門の場合、以下のような点を具体的に記述すると効果的です。
- 食事制限の内容や、それによる生活への影響
- 仕事への影響(重いものが持てない、長時間同じ姿勢でいられない、など)
ご自身が「当たり前」だと思っている困難さこそ、審査において重要な情報となります。
専門家である社労士に依頼するメリット
ここまでお読みいただき、「やっぱり自分一人で進めるのは難しそう」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。そのような時は、ぜひ障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。
専門家に依頼するメリットは、単に面倒な手続きを代行してくれるだけではありません。
- 受給の可能性や見込み額が事前にわかる
- 初診日の証明など、つまずきやすいポイントを的確にサポート
- 認定の可能性を高める、質の高い書類作成が可能
- 年金事務所とのやり取りや、書類の不備・差し戻しへの対応を任せられる
- ご自身は治療や生活に専念できる
当事務所では、初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所における障害年金受給事例
当事務所で実際に人工肛門(ストーマ)の障害年金申請をサポートさせていただいたお客様の事例をご紹介します。
【事例紹介】 人工肛門で障害厚生年金3級が決定し、遡及分約200万円、年間約70万円決定した事例
まとめ
人工肛門(ストーマ)を造設された方は、障害年金の受給対象となる可能性が十分にあります。
- 人工肛門を造設した場合、原則3級に認定される
- 他の症状とあわせて2級以上に認定されるケースもある
- 申請には「障害認定日の特例」があり、早期に申請できる
- 「初診日の証明」と「診断書」「病歴・就労状況等申立書」が重要
- 不安な場合は一人で抱え込まず、専門家に相談することが解決への近道
障害年金制度は複雑ですが、生活を支えるための大切な権利です。 よこやま社会保険労務士法人では、地域に密着し、お一人おひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを心がけております。
「自分は対象になるのかな?」「何から始めたらいいかわからない」 少しでもご不安があれば、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。ご連絡を心よりお待ちしております。
TOPへ戻る